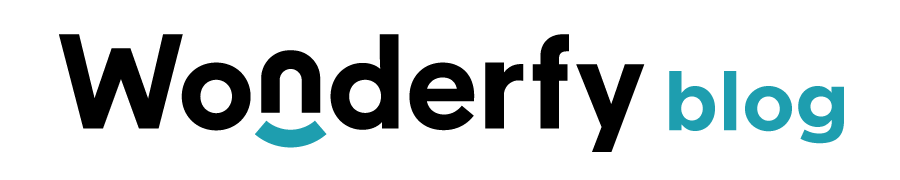「音楽を身近に感じ、音色を面白がってほしい。そして、自分の“好き”という物差しを大切にしてほしい」
ワンダーボックスの全楽曲を手がける作曲家の田中文久さんは、音楽に込めた想いをそう語ります。子どもたちの思考力や創造力を刺激するアプリの世界観は、どのようにして「音」によって彩られていくのでしょうか。
今回は、ワンダーボックスのサウンドトラックの配信を記念して、田中さんと、ワンダーファイで教材開発をしているディレクターのMikiさんに、楽曲制作の裏側やサウンドトラックの魅力などについてお話を伺いました。
ワンダーボックスサウンドトラック(全5枚組)

音楽だけでなく”身近な音”に耳を澄ませるうちに作曲家に
――まず、田中さんの自己紹介と、ワンダーボックスの音楽を手がけることになった経緯を教えていただけますか?
田中:作曲家の田中です。子どもの頃から、楽器の音色だけでなく、雨の音や風の音、街のざわめきといった身の回りのあらゆる音に耳を澄ませるのが好きでした。その音たちの鳴っている風景を想像したり、気に入った音をピックアップして全く別の景色を想像したり、、そういった体験が、現在の作曲家としての活動にも活きていると思います。
普段はワンダーファイさんとのお仕事に加えて、TVや映像作品の音楽を作ったり、現代音楽からポップスまで、幅広く音楽制作をしています。
ワンダーファイの教材音楽を制作するようになったきっかけは、ワンダーファイ代表の川島さんと共通の知人である花まる学習会代表の高濱正伸さんから、川島さんが新しく知育アプリを作るという話を聞いて、音楽を担当することになりました。どっちから言い出したかは正直覚えてないんですが(笑)
そのときに作った音楽が知育アプリ『シンクシンク』に使われています。その中の一曲である『好奇心とともに』という曲は、嬉しいことにtiktokで10億回再生されました。
子ども向けの音楽ばかりを作っているというわけではないのですが、自身が子どものころから好きな『トラや帽子店』というバンドがいて、その影響というか、根源みたいなのはあるなと思っています。
また、花まる学習会代表の高濱さんとは、「KARINBA」というバンド活動を行っています。子どもたちのために歌を作ったり、子どもたちと一緒に歌う活動をしていて、その影響も強くあると思います。
「大事なのはコンセプト」世界観を伝える依頼の裏側
――教材の音楽を依頼する際、どのように世界観のイメージを伝えているのでしょうか?
Miki:まず、教材自体のコンセプトや「子どもたちにどんな体験をしてほしいか」という核になる部分を社内のチームで徹底的に話し合います。その世界観が固まってから、田中さんにお願いするという流れですね。
イメージを伝える上で一番効果的なのは、やはり教材のビジュアルデザインをお見せすることです。例えば私が担当したワンダーボックスのアート教材の1つ『めいがのもりのコラトリエ』は『自分の感性を感じ、「自分なり」を楽しむ』というコンセプトです。
名画や他者の作品と触れる体験、コラージュという体験を通して、自分の好きや興味を感じたり、正解のない自分なりの世界を楽しんでもらえたら嬉しい、という思いでつくったコンテンツです。その当時にお伝えした資料の一部がこちらです。


時には、チーム内で「この映画のサントラの雰囲気が近いかも」といった参考曲を共有することもありますが、あくまで「方向性」の参考に留め、田中さんの自由な発想を尊重するようにしています。そこは長年ご一緒させていただいている信頼関係があるなと思っています。
――田中さんとしては、どのような情報があると作曲しやすいですか?
田中:1番ベストなのは、教材でやりたいことやコンセプトが明確に決まっていて、ビジュアルイメージがある状態ですね。それらの情報があるとインスピレーションをより明確にすることができます。参考曲がある場合も、あくまでワンダーボックスならではのオリジナリティをや、ワンダーボックスらしさを出すように心がけています。
――では逆に、最も難しい依頼はどんなものか聞いてみたいです。
田中:1番難しく、同時にやりがいがあったのは、コンセプトしかない、みたいな時ですね(笑)。どうしても制作に締め切りはつきもので、ディレクターのみなさんと一緒に並走しながらという場合もあります。想像力を最大限に働かせる必要があるので大変ですが、何もないところから世界が立ち上がっていく感覚は、作曲家として非常にエキサイティングな体験です。
あえて“子ども向け”を意識しない理由
――子ども向けの教材だからこそ、音楽制作で特に意識することはありますか?
田中:実は、「子ども向けだからこうしよう」という意識は、ほとんどありません。いわゆる「子どもっぽい」音楽を無理に作ろうとすると、どこか子どもの感受性をあなどるような、媚びた表現になってしまう気がするんです。
子どもたちは大人が思う以上に敏感で、本物を見抜く力を持っていると思っています。だから私は、年齢を意識するよりも、その教材が持つ世界観をいかに誠実に、そして豊かに表現できるかという点に集中しています。本気で作ったものは、きっと子どもの心にもまっすぐ届くと信じています。
――その「子どもに媚びない」スタンスが、ワンダーボックスの魅力に繋がっているのですね。
Miki:まさしく、そう思います!田中さんの音楽には、子どもたちの感性を決して見くびらない、というリスペクトが感じられます。だからこそ、大人が聴いても「いい音楽だな」と心から思えるクオリティになるのだと思います。
私たちは、子どもたちに質の高い本物の体験を届けたい、という想いを強く持っています。田中さんの音楽は、その私たちの姿勢を代弁してくれるような存在です。年齢で区切るのではなく、普遍的な「良さ」を追求することが、結果的に子どもたちにとって最も豊かな学びの体験に繋がると考えています。

世界観に没頭できるのは音楽があるからこそ
――そもそも、教材のためにオリジナルで音楽を制作することの重要性を、どのようにお考えですか?フリー素材などを使う選択肢もあったかと思います。
Miki:もちろん、教材の機能自体は、音楽がなくても成立するかもしれません。でも、子どもたちがその世界にぐっと入り込んで、夢中になって遊ぶ、あの「没頭感」は、やはり音楽の力がなければ生まれないものだと考えています。
フリー素材では、どうしても「どこかで聴いたことがある」感じや、世界観との微妙なズレが生まれてしまう。それは、まるでサイズの合わない服を着ているような、小さな違和感に繋がります。
その点、オリジナル曲は教材のためだけに作られたオーダーメイドの服のようなものです。ビジュアルや体験のデザインと音楽が完璧に融合することで、初めて生まれる相乗効果があります。その世界の奥行きや手触りがぐっと深まり、子どもたちの心を惹きつけて離さないのだと思います。

「自分の物差しで“好き”を見つけてほしい」ずんちゃか!に込めた想い
――ワンダーボックスのアート教材『ずんちゃかシーケンズ』は田中さんと一緒に制作した教材と伺いました。
田中:『ずんちゃかシーケンズ』子どもたちにとっての「音楽の入り口」になったらいいな、という想いを込めてみなさんと一緒に作りました。
そもそも、音楽の最初の第一歩とは何か。それは「聴くこと」だと考えたんです。自分の声や、身の回りにあるものを叩いた音。そうしたごく身近な音に耳を澄ませ、その響きや音色の違いを面白がってほしい、というのがコンセプトの核にあります。

――身の回りの音を録音して音楽を作る、というご自身の活動が反映されているのですね。
田中:はい、まさに!私はもう20年近く、日本中の様々な音を録音し、それを素材に音楽を作るという活動を続けています。
だから、このコンセプトは私の中からごく自然に出てきたものでした。道端の石ころや、空き缶、ペットボトル、段ボール箱。思いもかけないものから、驚くほど面白い音がすることがあります。そうした発見の喜びは、心をとても豊かにしてくれると思うんです。
「上手い・下手」や「正しい・間違い」といった評価から自由になって、ただ純粋に音と戯れる。その中で、自分の「好き」という物差しを見つけていってほしい。例えば、誰かが「この料理は美味しくない」と言っても、「でも、私はこれがすごく好きだ」と自分の心で感じたことを信じられる強さ。そんな、自分自身の感覚を肯定できる心を育む、ささやかなきっかけになれたら嬉しいですね。
▶身の回りの音を集めて、自分だけの音楽を作る(ワンダーボックス情報サイト「ファミサポ」)
「これは私の趣味です(笑)」制作者のお気に入り曲は?
――サウンドトラックの中で、特に思い入れのある曲を教えてください。
Miki:たくさんあって選ぶのが難しいですが、やはり自分が企画の立ち上げから深く関わった『めいがのもりのコラトリエ』の曲には、思い入れがあります。
コンセプトや世界観を練り上げ、デザインチームと何度もやり取りを重ねて作り上げた世界でした。そこに田中さんが曲をつけてくれた時、想像を遥かに超えるほど素敵に世界が完成して、鳥肌が立ったのを覚えています。
私たちが目指した、自己との対話という、静かだけれど内側から躍動するようなイメージが、音として完璧に表現されていました。

『めいがのもりのコラトリエ』の楽曲
ーアトリエにて
ーインスピレーション
ー森の美術館
個人的には『ポルトのほしさがし』や『セルトンのふしぎなタブレット』の少し機械的でリズミカルな曲も大好きです。

『ポルトのほしさがし』の楽曲
ーほしを眺める
ーStar Seeker

『セルトンのふしぎなタブレット』の楽曲
ーライフゲーム
ーオートマトン
――田中さんのお気に入りの曲を教えてください。
田中:私も『セルトンのふしぎなタブレット』は気に入っていますね。そして『めいがのもりのコラトリエ』の曲は、展覧会のものも含めて全部好きです。
『ナゾロボ〜ナゾトキロボットファクトリー〜』は、かなり趣味に走った曲でお気に入りです(笑)。もちろん曲全体は工場のコンセプトに沿っているのですが、ミニマル・ミュージックのような反復するフレーズで始まる冒頭部分は、完全に「私が今作りたい音」を詰め込みました。遊び心満載で、作っていてとても楽しかった一曲です。

『ナゾロボ〜ナゾトキロボットファクトリー〜』の楽曲
ーわくわくファクトリー
ー制御モード
「自分の軸を持てるようになってくれたら」音楽が育むものとは
――このサウンドトラックを、どんな人に、どんな風に楽しんでほしいですか?
Miki:本当に、あらゆる人に聴いていただきたいです。ワンダーボックスの音楽は、子ども向けという枠には収まらない、普遍的な魅力を持っていると思います。ですから、年齢や性別を問わず、たくさんの方に届いてほしいですね。
お家でのリラックスタイムや、お仕事中のBGMとして気軽に流していただくのもいいですし、時にはじっくりと音の細部に耳を傾けて聴いていただくのも、新しい発見があって面白いかもしれません。
この音楽が、日々の暮らしにちょっとした彩りや、わくわくする気持ちを添えることができたら嬉しいです。
――では最後に、田中さんが音楽を通じて、子どもたちに最も届けたい想いは何でしょうか?
田中:ワンダーボックスのサウンドトラックを聴いて、「好き」とか「楽しい」、あるいは「面白い」「不思議な感じがする」「なんか違和感ある」「ここちょっと変かも」とか、子どもたち自身の心で感じて、判断してほしい、それが一番の願いです。
世の中の評価や情報、周りの意見に流されるのではなく、「自分はこう感じる」という確かな物差しを、自分の中に作っていってほしい。たとえ世間的には評判が良くなかったり点数が低かったりする料理があったとしても、「でも私は、これが美味しいと思うんだ」と言えるような、しなやかな強さ。
私の音楽が、子どもたち一人ひとりが持つ、その人だけの「好き」や「楽しい」という大切な気持ちを、そっと後ろから支えてあげられるような、またそんな大切な気持ちを見つける一助になったりするような、そんな存在であれたら、作曲家としてこれ以上の喜びはありません。
インタビューは以上です。
今回、楽曲を制作している2人のお話を聞き、音楽を身近に感じることの豊かさや、音楽が作る世界観の魅力を知ることができました!
ワンダーボックスのサウンドトラックは、ワンダーボックスでお届けする教材と同様、STEAMに合わせて5枚のアルバムで配信しています。サウンドトラックをご自宅のリラックスタイムや作業BGMとしてぜひご活用ください!
各種配信サイトへは以下のリンクから





ワンダーファイ公式YouTubeでは全曲の再生リストを作成しています!

プロフィール

田中 文久
Fumihisa Tanaka
作曲家・ソニフィケーションアーティスト・サウンドプログラマー1986 年生まれ、長野県松本市出身。
松本深志高校、東京藝術大学音楽環境創造科を経て、2010 年、東京藝術大学大学院音楽研究科を修了。
音楽に関する様々な技術やテクノロジーを駆使し、楽曲制作のみならず、空間へのアプローチや研究用途、最近では、あらゆるものを音に変換する「ソニフィケーション」を用いた制作・研究・開発等、音楽の新しい在り方を模索・提示している。
主な作品に、教育アプリ『Think! Think!』(2017年Google Play Award ファイナリスト, 2023 APEC Digital Innovation and Educational Opportunities 第1位)、教育アプリ『WONDER BOX』、映画『映画愛の現在』『アトモスフィア』、NHK 特集ドラマ『ももさんと7人のパパゲーノ』(2022年 文化庁芸術祭参加作品)、NHK Eテレ『#8月31日の夜に。』(2018年イタリア賞受賞番組)など。
公式サイト:https://www.fumihisatanaka.net/

Miki
ワンダーファイ コンテンツディレクター
子どもたちが、自分なりの表現や発見を楽しむコンテンツ企画に強みを持つ。知育アプリ「シンクシンク」ではUI/UXデザインに携わったほか、STEAM通信教材「ワンダーボックス」では、名画を「創作の素材」として扱い、自由に切り貼りするコラージュコンテンツや、身の回りの音を録音し、その「音色」をキャラクターに変換して音楽を創作するユニークなアプローチのコンテンツも生み出した。正解のない問いを通じて感性を引き出す、「自分らしさ」を育む体験デザインを大切にしている。