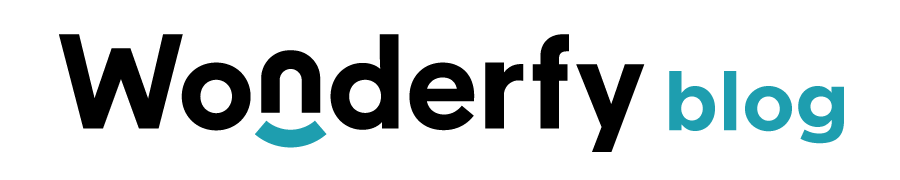「子どもの力を伸ばすには○○が必要」「これからの時代に求められるのは○○力」、そんな教育論が世の中にあふれる今、本当に大切なことは何なのでしょうか。
世界150カ国300万人以上が使う知育アプリ『シンクシンク』や、遊びながら思考力・創造力を育むSTEAM教材『ワンダーボックス』。これらを手がけるワンダーファイの代表でありファウンダーの川島が大切にしているのは、子どもたちの「考えるって、楽しい!」という気持ちを引き出すことです。
なぜ「わくわく」が学びにとって大切なのか。 そして、そこにどんな思いを込めて教材を作っているのか。
これまで1万人以上の子どもたちと関わってきた川島に、自身の原体験を交えて、ワンダーファイが大切にしている学びについてインタビューしました。
「算数好き」の少年時代 。考えることに夢中だった日々
──まずは、幼少期について教えてください。どんな子どもでしたか?
川島:幼少期は、良い意味で放っておかれていましたね。「勉強しなさい」と言われた記憶もないし、自分でも特別勉強が好きだと感じたことはありませんでした。ただ、隣のおうちでやっていた学研教室に通ったときに「あれ?自分、算数得意かも」と初めて気づいたんです。
──他には、どんなことが好きでしたか?
サッカーも好きで、試合の流れを頭の中でシミュレーションしながら戦略を立てることに夢中でした。今思うと、あの頃から「考えること」を自然と楽しんでいたんだと思います。
それから、祖父が囲碁や将棋に夢中になっている姿も大きかったですね。遊びに行くたびに「そんなに楽しいものなの?」と興味を持てたのも考えることを好きになったきっかけの1つだと思います。

教育業界に飛び込むきっかけと決意
──教育の道に進んだのは、何がきっかけだったんでしょうか。
川島:教育の世界に足を踏み入れたのは、大学3年生の頃でした。学習塾『花まる学習会』の「こんな問題作ってみませんか?」という広告を見つけて、興味を惹かれて応募しました。そしたら、代表の高濱正伸さんが私の作った問題を見て「この問題を作った人を連れてきて!」と言ってくれました。それがきっかけで、高濱さんの下でアルバイトを始めました。
──就職先も、最初から教育業界に決めていたのですか。
川島:いいえ。就職については、最初は一度企業に勤めて経験を積んでから教育に戻ろうと考えていたんです。
でもあるとき高濱さんと、高校時代の恩師の井本陽久先生と3人で食事をしました。そのときに「明治時代からずっと続いていた教育というものが、高濱さんや井本先生を中心に今まさに変わろうとしているんだ」と感じる出来事があり、自分もこの流れに身を置きたい!と強く思ったんです。その翌日には、決まっていた企業の内定を辞退して、花まる学習会に就職することに決めました。
教育にかける情熱と挫折、そこから意図せず得たヒント

──キャリアのスタートとなった『花まる学習会』ではどんな経験を積んだのですか。
川島:『花まる学習会』では、教室での授業や野外体験など、子どもたちが楽しそうに学ぶ姿が素晴らしくて、とても楽しく働いていました。
ただ、その一方で、新しいことに挑戦したいという気持ちと、教室に通えない子どもたちにも楽しい学びを届けたいという気持ちがあり、児童養護施設を紹介してもらい、活動を始めました。
──施設での活動はいかがでしたか?
川島:はじめのころは、「この子たちを自立させるんだ」「学校にいけるようにするんだ」という志に燃えながら活動を始めたものの、そうした意気込みは、むしろ子どもたちを傷つけているんじゃないかと感じることがありました。
例えば、子どもたちの学習の進度に合わせ、良かれと思って小学5年生に2年生の問題を渡すと、せっかく来てくれたお兄さんたちにいいところを見せたいのに、できない自分を見せることになってしまう。そうなると、勉強は進まないし、子どもたちは失敗を怖がるようになってしまいました。
──良かれと思っての行動が、裏目に出てしまったと。
川島:そうなんです。そんなとき、「勉強しないよりはいいか…」と自作のパズル問題を持って行きました。私たちの主要サービスである知育アプリ『シンクシンク』のような問題で、何年生用などの表記もせず、ゲーム感覚で「あ、できる!」と感じられる内容にしたら、子どもたちは夢中になって取り組んでくれました。
すると、「もう終わり?」「じゃあ宿題やろうかな」と自分から勉強を始めるようになって、施設の方からも「成績が上がりました」と驚かれるほどでした。
この一連の体験から、子どもにとって、「学ぶ場」や「学ぶこと自体が楽しい」ということがまず先にあって、知識やスキルは、その後自然に身についてくるものだ、ということを私に教えてくれました。
その後、『栄光学園』のプログラムでフィリピンにホームステイする機会があって、井本先生に同行させてもらいました。そこでも自作の教材を持って行ったのですが、5歳から19歳ぐらいまで、さまざまなバックグラウンドの子どもたちが「こんな楽しさ味わったことない!」という様子で、背中をゾクゾクさせながら夢中になってくれたんです。
それを見て、『もっと喜んでもらいたい!』という気持ちがどんどん大きくなっていきました。
そこから、教材を「言語に関係なく楽しめて、考える楽しさを伝える」方向性でブラッシュアップして、モンゴルや東ティモールなど、さまざまな国に持って行ったんです。どの国でも、子どもたちは同じように躍動して楽しんでくれました。
「これを世界中に届けたい」という思いが決定的になり、仲間を集めて始めたのがワンダーファイです。
正解のない時代に、「学びを楽しむ子」が強い理由

──ワンダーファイ設立から約10年が経ちました。今はAIが急速に進化し、教育の常識も変わりつつあります。これからの教育はどうなっていくと思いますか?
川島:私が子どもの頃は、「いい大学に入って、いい会社に入れば安泰」という価値観がまだありました。でも今は、10年後どころか数年後の未来さえどうなるか分からない時代です。変化が急すぎて「それが子どもの人生にとって正解なのか?」という見通しがなかなか立たないというか。
言われたことをただこなすような作業は、AIが得意とするところです。そうなると、知識をたくさん詰め込むことではなくて、「自分はどう考えるか」「何を面白いと感じるか」という、自分だけの視点や問いを持つ力こそ大事になってくるんじゃないかと思うんです。
私が以前に担当していた算数の教室で、あまりに授業が楽しみで、始まる前からぴょんぴょん飛び跳ねていた5年生の女の子がいました。保護者の方から見れば、つい「落ち着きなさい」と言いたくなるところですが、彼女は考える楽しさを全身で表現していたんです。その素直さは、その後の算数の力の伸びにも大きくつながったと私は思います。
子どもの反応を直接見て、教材を磨いていく
──教材をつくるとき、どんなことを大事にしているんでしょうか。
川島:ワンダーファイでは「研究授業」を実施しており、教材を完成させる前に子どもたちの前に出して、全員が楽しめるかを完成の基準としています。もし1人でも『面白くない』と感じる子がいれば、それは教材にまだ改善が必要な証拠です。
たくさんのデータを集めて改善するという手法もありますが、私たちにはまず目の前の子どもたちを楽しませるやり方がフィットしていると感じます。
ITを活用すると、間違えた問題を繰り返し出題すれば正解率が上がるという設計もできます。でもそれは、私たちのやりたいことではありません。間違えた問題ばかりが出てきたら、子どもは嫌になってしまいますよね。
遊び感覚で学べる教材を作るには、チーム体制も大切です。コンテンツクリエイター、デザイナー、エンジニアみんなで子どもの反応を見ながら、『こういうふうにしたら、子どもの反応がよかった』と意見を交わしながら教材制作を進めていけることは私たちの強みです。
考えることに対するスペシャリストが、子どもの反応をつぶさに確認しながら改良していくというプロセスは、良い教材を作る上で不可欠です。
──直接子どもたちの声を聞かれているんですね。研究授業で、反応が良くないこともあるんですか?
川島:はい、子どもたちはつまらないものにはつまらないとはっきり言ってくれるし、態度にも出るので、教材を初めて試すときはいつもドキドキします。だからこそ『この子たちに楽しんでもらいたい』という気持ちが自然と湧いてきます。
世の中には、面白いことやわくわくすることがたくさんあります。それらを「こんな面白いものがあるよ!」と伝えて、その子が自分らしく人生や縁を広げるきっかけになるような教材やサービスを作っていきます。