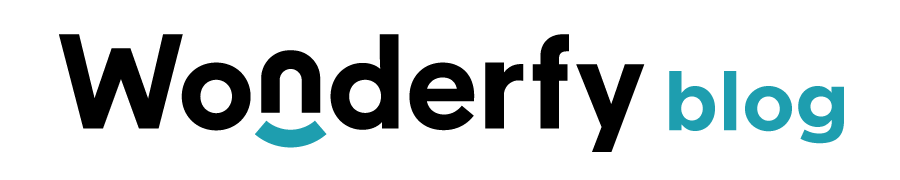2025年7月22日、全世界で同時リリースされた新作ゲーム『ポケモンフレンズ』。
ワンダーファイは、思考力が育つ知育アプリ『Think!Think!(シンクシンク)』で培ったノウハウを活かし、問題提供および一部開発を担当しました。
詳細については、以下のプレスリリースをご覧ください。
「ポケモンの新作ゲーム『ポケモンフレンズ』の問題提供および一部開発をワンダーファイが担当」
「考えることが楽しくなる、ひらめき問題がたくさん遊べるゲーム」をテーマに掲げた本作は、遊びの中に学びを自然に溶け込ませることで、エンターテインメントと教育の新たな可能性を切り拓いています。
今回のリリースを記念し、株式会社ポケモン 押野洋介さん、教育経済学者 中室牧子先生、そしてワンダーファイ代表 川島慶 による特別鼎談を実施しました。
登壇者プロフィール
押野 洋介
株式会社ポケモン 開発プロデュース本部 アプリ事業部 テクニカルディレクター
2005年に任天堂株式会社に入社してゲーム開発に従事。2019年に株式会社ポケモンに入社。2020年に子どもの歯みがきを楽しく習慣化するゲームアプリ『ポケモンスマイル』を開発。『ポケモンフレンズ』では、プロデューサー兼ディレクターを担当。
川島 慶
ワンダーファイ株式会社 代表取締役 CCO(Chief Creative Officer)/ ファウンダー
算数・数学好きが高じ、思考力を育む問題集や教材開発に長年携わる。2014年にワンダーファイ(旧:花まるラボ)を創業。『ポケモンフレンズ』では教育監修と問題設計を担当。著書に『自分の頭で考える子に育つ学ぶ力の伸ばし方』がある。
中室 牧子
慶應義塾大学 総合政策学部 教授 / 教育経済学者 / デジタル庁シニアエキスパート。
教育を経済学的な手法で分析する「教育経済学」が専門。データに基づいた教育政策や子育てに関する提言で知られ、著書に『学力の経済学』『科学的根拠(エビデンス)で子育て 教育経済学の最前線』がある。

ポケモンとワンダーファイが生み出す「面白さ」と「教育的価値」
――早速ですが、『ポケモンフレンズ』は、どのようなゲームなのでしょうか。

押野さん: このプロジェクトは「ポケモンを通して子どもたちの成長に貢献したい」という思いから始まりました。約2年前から議論を重ね、ワンダーファイさんの「子どもの知的なわくわくを引き出す」という知見と、ポケモンが持つゲーム性を組み合わせることで『ポケモンフレンズ』が生まれました。
遊ぶたびに“できた!”が見つかる難易度設計により、ワクワク感や達成感をポケモンと一緒に体験できます。その積み重ねが自然と「考える習慣」を育み、「考えること自体が楽しい」と感じてもらえることを目指しました。
――ワンダーファイとして、このコラボレーションにはどのような思いがありましたか?
川島: 私たちのミッションは「世界中の子どもの“知的なわくわく”を引き出す」ことです。『シンクシンク』も「考えるって、楽しい!」と子どもたちに感じてもらいたくて始めました。その思いをより広く届けるには、世代や国境を越えて愛され続けているポケモンさんは最高のパートナーでした。
難しい問題に挑戦するにはエネルギーが必要ですが、それを支えるのが「快感の蓄積」です。たとえば、問題を解いたときにポケモンが笑顔で喜んでくれる。その小さなご褒美が達成感を増幅し、次の挑戦につながります。今回のコラボで、その仕組みをうまく形にできたと思います。


中室先生: 確かに、やらされている勉強は続きませんよね。子どもが学び続けられるかどうかは、結局「自分でやりたい」と思えるかどうか。つまり意欲という内的モチベーションに支えられているのだと思います。
子どもの意欲を引き出す“ちょうどいい難しさ”
――ここからは教育的な側面を掘り下げていきたいと思います。中室先生は、『シンクシンク』の効果を実証実験で明らかにされていますよね。
中室先生: はい。『シンクシンク』については、カンボジアで大規模な実証実験(※)を行い、認知能力(学力)だけでなく、意欲といった非認知能力も高める効果が確認されています。そこにポケモンや継続を促す仕組みが加わったという点で、『ポケモンフレンズ』も良い効果が期待できると思います。
(※)『シンクシンク』実証実験について
ワンダーファイは、慶應義塾大学・JICA・カンボジア教育省と共同で、1,636名の小学生を対象にランダム化比較試験(RCT)を実施しました。3ヶ月間+8ヶ月間の延長調査の結果、算数の成績は +5.6ポイント、IQスコアは +7.0ポイント 向上。さらに、学習意欲や非認知能力の向上にも有意な効果が確認されています。 詳細はこちら
――『シンクシンク』のどんな点が、子どもの力を伸ばすことにつながったとお考えですか。

中室先生: 認知能力とは突き詰めれば「考える力」です。『シンクシンク』は、まさにその「考える力」を育むというコンセプトで作られている点が大きいでしょう。
またICTを活用し、一人ひとりに最適なレベルを提示する「アダプティブラーニング」を実現している点も重要です。学びは累積的なので、簡単すぎても難しすぎても意味がありません。最適なレベルでこそ力が伸びるのです。
――「アダプティブラーニング」の要素は、『ポケモンフレンズ』にも活かされているのですね。
川島: そうです。『シンクシンク』で得られたデータを活用し、子どもが“心地よく、少しだけ挑戦的”な問題に取り組めるよう難易度を細かく設計しました。
押野さん: ゲームなのでスコアは出ますが、オンラインランキングはあえて導入していません。他人と比べてやる気をなくす子もいるからです。大事なのは「前の自分よりできた」と感じてもらうこと。報酬も“強い人だけが良いものをもらえる”のではなく、毎日続ければ誰でも楽しめる仕組みにしています。
――なるほど。他人と比べるのではなく「自分の成長」を感じる仕組みが大事なのですね。
中室先生: その通りです。相対評価が成長を促すのは一部の上位層だけだという研究結果があります。大人数の中では多くの子が「自分は小さい存在だ」と感じてしまい、意欲を失いかねません。これを経済学では「井の中の蛙効果」と呼びます。だからこそ「過去の自分と比べて少しでも成長した」と実感できる仕組みは、すべての子のモチベーションを支えるものになると思います。


AI時代を生き抜く「考える力」
――最後になってしまいますが、これからの時代を生きる子どもたちへのメッセージをお願いします。
押野さん: 今は学校でiPadが配られるなど、子どもたちがデジタルに触れるのは当たり前になっています。その中で、保護者の方が安心して遊ばせられて、しかも子どもの役に立つものを選択肢として届けたいと思っています。『ポケモンフレンズ』が遊びながら「考える力」を育むきっかけになれば嬉しいです。
中室先生: 人生100年時代、大人になっても新しいことを学び続ける必要があります。そのとき「勉強は苦行だ」という感覚しかないと続きません。だからこそ、幼少期から「考えるのは楽しい」と思える体験を積み重ねておくことが、長期的にとても大切です。
川島: まさにその通りです。これまでは「良い大学に入れば安泰」という戦略もありましたが、今は20年後に必要な力を誰も予測できません。だからこそ、どんな時代になっても変わらない、自分のワクワクを原動力に「考えることを楽しむ姿勢」を持てるかが大切だと思います。
――なるほど。未来を生きる力の核心ですね。
川島: 答えのない問いに挑むには、ひとつの正解を求める学びとは違い、試行錯誤を繰り返しながら向き合い続ける姿勢が必要です。そうした過程の中では「わかった!」「気持ちいい!」という小さな快感を積み重ねていくことが欠かせません。その土台を育むためにも、『ポケモンフレンズ』を通じて、多くの子どもたちに「考えるって、楽しい!」と感じてもらえたら嬉しいです。

編集後記
遊びと学びの境界を軽やかに越える『ポケモンフレンズ』。
子どもたちがそこで見つける「考えるって、楽しい!」という感覚こそ、AI時代を生き抜く力の種になるのかもしれません。
ワンダーファイもまた、ミッションである「世界中の子どもが本来持っている知的なわくわくを引き出す」の実現に向けて、他作品とのコラボレーションや、教材やイベントなど様々な形で「考えるって、楽しい!」という体験を子どもたちに届けていきます。
※画面は開発中のものです。
©2025 Pokémon. ©1995–2025 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。