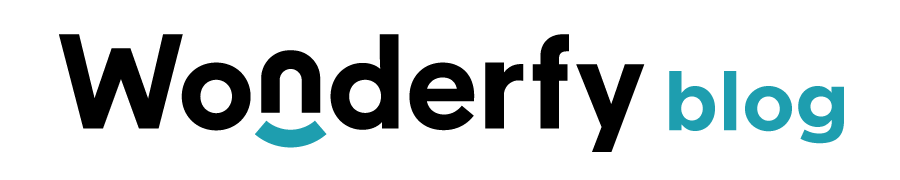スクールFC 仁木 耕平

親子で設定した目標に挑んだ日々の「終わり」に
2017年度の中学受験が、終わりを迎えつつあります。私自身が進学塾で2年間担当してきた子どもたちの入試も終了し、すべての子どもたちが、本当に素晴らしい結果を残してくれました。受験に向き合われた全てのご家庭に、心から敬意を表します。
今回は、私やその周りの方の経験をもとに、第一志望に「不合格」となった時、ご両親は、わが子にどう接するのが良いかを書いていきたいと思います。
「不合格」―そのときに周囲の大人ができること
親子で目標設定をして、受験に臨む。 目標を設定して、そこに向かって頑張ることは、その子が具体的なイメージをもって頑張るために必要なことです。それがとても高い目標であったとしても、親子が納得ずくであれば構わないと思います。一方で、受験は「頑張ったから全員が受かる」ものではありません。努力を重ねることで、合格に極限まで近づくことはできます。しかしそれでも「確実」はありません。上位にいけばいくほど、たとえば足の速さと同じで、どうしても埋められない力の差が立ちあらわれてくる、という面もあります。
目標を設定して頑張った、その末に結果が出る。その結果が、たとえば「第一志望には不合格。第二志望に進学決定」であったら。進学塾とそのスタッフは「その受験は失敗だった」という捉え方をすべきだと思います。どんなに本人の実力とかい離した受験であったとしても、顧客の望みをかなえることができなかったわけですし、その望みの内容やあり方を、数年間のコミュニケーションの中で、よりよいと思われる方向に変えていくこともできなかったのだから。あるいは親が、心の中では「うまくいかなかったな」と思ってしまうことも、仕方がないことかもしれません。
しかし、子ども自身が「自分の受験は失敗だった」と思い知らされる必要は、ない。ましてや、親に切って捨てられるような形でそう思い知らされる必要など、絶対にない。そう思うのです。
目指していた結果にたどり着けなかった。そのときにこそ、子どもの受験に対して、親ができることがあります。
「子どもが、自分の受験を肯定できるように。行きついた新しい場所に、時間はかかったとしても、誇りを持つことができるように。前を向けるように」。そのための関わりや言葉かけが、その子がこれから先の青春時代と人生とを前向きに生きつづけていくために、周囲の大人たちがしてあげられる、尊いことだと思います。
受験の結果で自己肯定感を失うことこそが、最大の「失敗」
人が生きていく上で大切なのは、自己肯定感です。自らの頑張りや持っている才能を活かして、「結果を出すことで」自信を身につけていく。それも大切なことです。 しかしそれと同等か、それ以上に大切なのは「結果の出せる自分」だけではなく、「ありのままの自分」への肯定感ではないでしょうか。
ここで言う「ありのままの自分を肯定する」ことは、怠惰さや志の低さを意味するものではありません。人生のさまざまな場面で、どんなに頑張っても、どんなに考えても、こうでしかあれない自分に行きついた、そのときに「これが自分なんだ。そして、それでいいんだ」と肯定できるかどうか、ということです。
この自分で、戦っていく、生きていくんだ。行きついたこの場所で/ここから、よりよくなっていくんだ。幸せになっていくんだと、前を向ける。そんな自分をまるごと受け入れて、ときに、満ち足りることができる。行きついた自分の場所を、周囲を、大切にすることができる。愛することができる。それが「足るを知る」であり、生きていくために必要な自己肯定感ではないかと思います。
そのような自己肯定感を持てるかどうかには「ありのままの自分を、誰かに心から受け止めてもらった経験の有無」が、深くかかわってきます。努力を重ねてきた末の「不合格」という結果に、落ち込まない人間はいません。ふがいない時期があった、絶対値として、やるべきことに向き合いきれなかったとしても、3年間その子なりに頑張ってきたのです。自分にはじめて無慈悲に突きつけられる「あなたは、うちの学校には入れません」というメッセージに、子どもは心底打ちのめされます。大切なのは、そのときに何と言ってもらえるかです。それこそが、その後の人生を左右する局面だ、と言っても過言ではありません。
肯定する。何度でも、何度でも
不合格が「周囲の人たちに支えられながら、届かなかった自分を自分で受け止め、前に進むことができた」という経験になれば、それは「乗り越えの経験」になります。不合格を知って、呆然としたまま自宅に帰り、ストーブの前でぽろぽろと泣き出してしまった自分に、母親がそっと飲ませてくれたホットミルクの味が、今の自分を支えているんです、と教えてくれた、幸せに今を生きている知人がいます。「どんな結果でも、受け止める。肯定する。」社会が絶対評価でしか見てくれないからこそ、いくら言い訳しようと覆しようがない結果が突きつけられるからこそ、それは、親にしかできないことです。
「結果は出た。でも、あなたは最後、本当に頑張ることができていた。近くで見ていたよ。だからきっと、次も頑張れる。胸を張って生きていきなさい」「途中では厳しいこともたくさん言った。第二志望だったかもしれない。でも、あなたはずっと、頑張っていた。格好よかったよ!そして、通うことになったこの学校は、私たちが胸を張って勧められる、本当にいい学校だよ」そんなふうに、何度でも、何度でも言ってあげることです。
失敗を断罪されることで、子どもが背負ってしまうもの
子どもたちは、人生にたった一度しかない「子どもの時間」を過ごしています。そして、子どもの時期にあったこと、感じたことは、その人のその後の人生を「覆うもの」となる可能性があります。10歳から12歳の3年間も、また然りです。導き方を間違えなければ、どの子もその子の手持ちの力で、本当に一生懸命やります。ときに向き合えない、逃げてしまう、そうしたことも含めて、今のその子のすべてです。なんとか向き合えるように、求める結果に向かって伸びていけるようにと、周囲は必死になり、本人も応えようとします。
過程に至らなさがあったとしても、本番が近づくほどに、子どもたちは受験を自分のこととして捉え、必死に頑張ります。自覚するのが遅ければ、そこから取り返せるものには限りが出てしまうケースもあります。 それでも、そこからはひたむきに頑張ります。早くから自分に向き合い、頑張ることができていた子たちもいます。
そうであっても、上位であればあるほど、結果がどうなるかは誰にもわからないのです。
多くの大人たちが、日々社会の中で、「結果」にさらされて生きています。過程がどんなによいものでも、どれだけ頑張ったのだとしても、結果が出せなければ認めてはもらえない。その実感があるからこそ、大人たちはその論理をそのまま、子育てに、子どもの受験に、持ち込もうとします。失敗したら、失敗だと断じること。それこそが、社会の荒波の中を生きる自分が、子どもに対してしてあげられることだ。厳しさに直面させることが、次こそは頑張ろうと奮い立つ心に結びつくのだ。そう信じているのだと思います。
それは誤解だと、はっきり伝えたい。なんとかして、伝えたいのです。
「人生では、結果だけが残る。だから結果を出せ」という言葉は、仕事上の真実ではあるかもしれませんが、12歳の子どもにとっては恫喝であり、呪いです。中学受験は、それ自体をやり直すことは二度とできないライフイベントです。結果が全てであり、結果が出せなかった君の時間に価値はない、と断罪されれば、子どもの人生には、次こそは奮起しようという前向きな意志ではなく、断罪された経験の方が強く残ります。
子ども時代に、何年もかけて精一杯頑張った自分を、ばっさり切って捨てられた経験は、一生引きずる心の傷になり得ます。親の発したそうした一言が、ときに「認められることを、ゆらぐことがない自信を求めて、いつまでもさまよい続ける人」を生みだしてしまう。人間は、発達段階の中で十分に得ることができなかった承認や愛情を、どこかで取り返そうとしつづけてしまう生き物だからです。
ゆらぐことのない自信を求めて、さまよい続ける大人
以下は私が経験した実際の話です。
人生の節目節目で、やっとの思いで手に入れたがんばった結果を、父親に絶対評価で折られつづけた、ADHDの診断を持つ子の半生。アルバイトの採用面接にきた「誰もが羨む最難関校出身で、今は有名私大に通う子」が、覇気なく「自分は落ちこぼれなんで…」と繰り返したときに思ったこと。小3から小5にかけて、通っていた塾の先生と父親に「御三家以外は学校じゃない」と刷り込まれ続けた結果、小テストや宿題で、答えを写すことをやめられなくなってしまった女の子。父親が家に帰ってくるたびに「一番の高みを目指すというのに、おまえはこんな問題もできないのか」と恫喝されつづけ、父のいないところで幼児がえりをしてしまった子(この子は、受験期の途中で父親の心のありかたが変わって、持ち直すことができました)。
或る人を支配した「父親の言葉」
以前、書籍の編集担当でお世話になっているIさんが自身の経験をいくつか語ってくれました。
Iさんが現在つとめる出版社に入社する前、転職希望者のための「塾」に通っていたことがあったそうです。Iさん自身は、別の出版社からの転職を目指してのことでしたが、特定の業種をターゲットにした塾ではなく、彼の「同期」にはさまざまな人がいました。 疲れた様子の元プログラマーの男。「前職の体操服屋さんがつぶれちゃって…」という、何だかちぢこまった、冴えない印象の男。
その中にひとり「東大出身で、超大手コンサル会社を辞めてきた」という、Iさんの言葉を借りれば「圧倒的にハイスペックな」男がいました。「なぜこいつがこんな場所に?」だれもがそう思うような奴でした、とIさん。親しくなり、話をする中で、彼が転職をする動機を聞くことができたそうです。
「自分は中学受験で、目指していた学校に入れなかったんです。そのとき、父親に「お前の受験は失敗だったな」と、ばっさり斬って捨てられてしまいました。それ以来、「絶対にゆるがない自信がほしい」と願いつづけて、今も高みを目指しているんです。」
「絶対にゆるがない自信って言ったって、あなたもう、これまでの経歴が十分そうじゃん。これ以上、何を?」それが、Iさんの率直な感じ方でした。
「塾」を通じて、Iさんも他の同期たちも、自分のあらたな道を見つけていきました。 みんなさまざまな業種で、大活躍しているといいます。現在の出版社で大活躍中のIさんもその一人です。元プログラマーだった人は、大手ゲーム会社に入社し、誰もが知っているタイトルのヒット作を開発しました。元・体操服屋の男は、関西に移り住んでプロボクサーになり、傍らで会社経営をしているそうです。
しかし、「圧倒的ハイスペック」の彼は、塾が始まってほどなく休みがちになり、やがて塾に来なくなってしまいました。塾に来なくなってしまってからも、Iさんはしばらく、彼と連絡をとり続けていました。結局彼はその後、小さなコンサル会社を転々とする中で、お店で出会った女性に入れあげて、数百万あった貯金も使い果たし、最後はその「彼女」が会社に来て「彼は体調不良のため、数か月会社を休みます」と告げたそうです。それ以後、Iさんが連絡をしても、彼から返事が来ることはありませんでした。
父親は、「彼をこんな結果で満足させてはならない」と考えて、彼の受験の結果を切って捨てたのでしょう。ですが、その満たされなさは、言葉を選ばずに言えば、無駄なものだと思います。不毛で、不必要なものだと思います。
「強くなれ、甘くないんだから」という思いでかけた言葉は、その子のその後の歩みに始終ついてまわり、半生をくじくようなものになってしまった。「おまえは十分すごいよ。次は頑張れよ」もし、かけられた言葉がそういう言葉だったら、また、変わったのでしょうか。
Iさんはもう一つ、こんな話もしてくれました。経営者の父親をもつ知人がいます。彼の父親は非常に厳しい人で、その人がどんなに頑張っても、決して褒めてくれることはありませんでした。受験で家族の望む結果を出しても、本当に何一つ、言ってくれなかったそうです。
「いつか、父親に自分を認めさせたい」その一心で頑張り続け、彼自身も経営者になり、やがて、自社ビルを建てるまでになりました。父親が、その自社ビルを見て初めて「おまえはすごいよ。俺はお前に負けた」と言ったのだそうです。はじめて父親がそんなことを言ってくれて、その知人は、泣いて喜んだのだそうでした。
彼が父親にこういう言葉をかけてもらうまでの半生の中で、どんなことを感じてきたのかはわかりません。何とも言えない。ただこの話には、先の「ハイスペック君」の話と根を同じくする部分があると、私は思います。
子どもの出した結果に、父が、母が、どんな言葉をかけるか。
子どもは、その言葉を、そのときの思いを、ずっと背負って生きていきます。